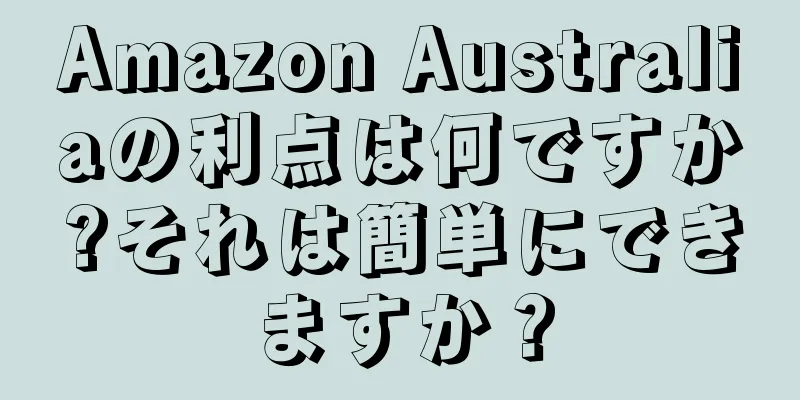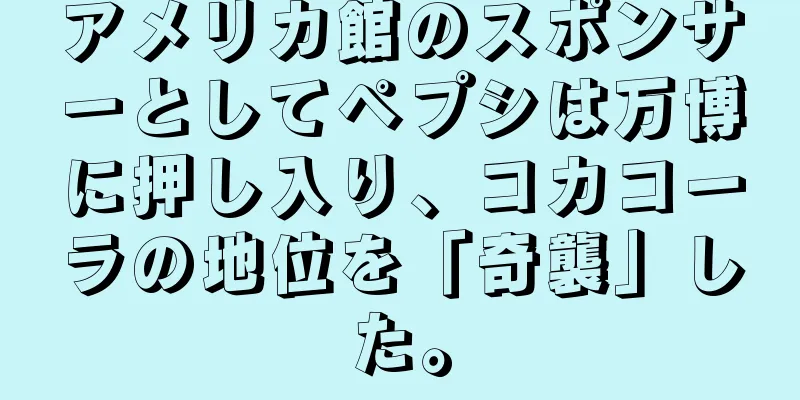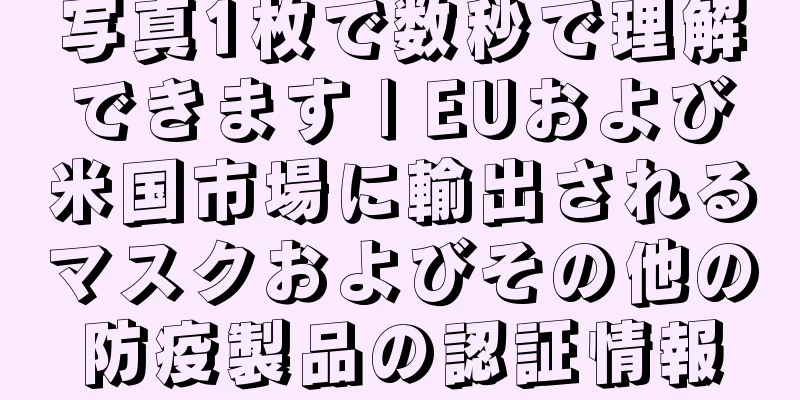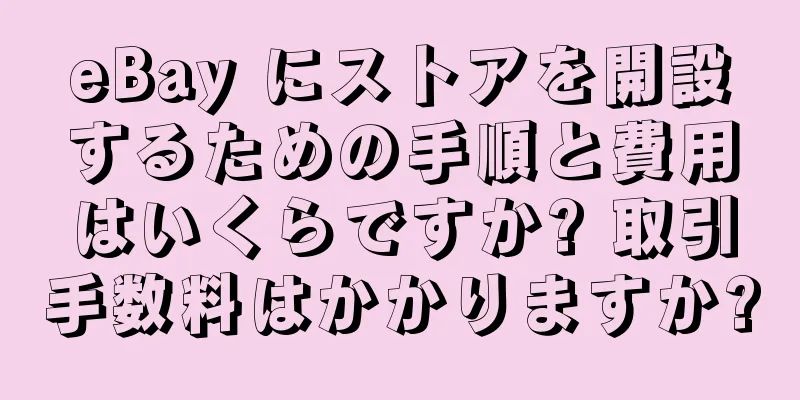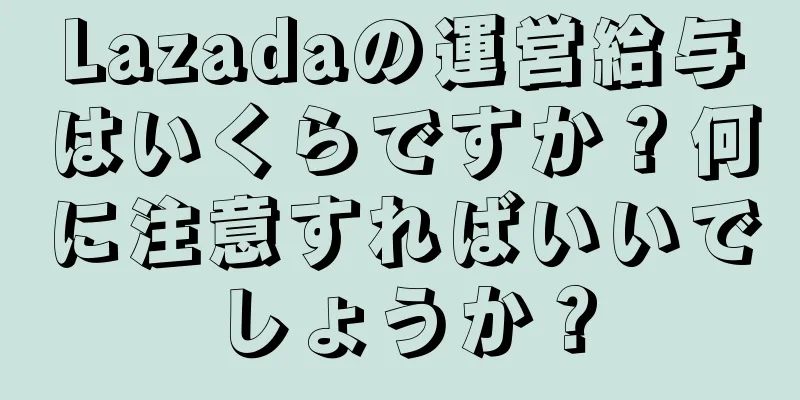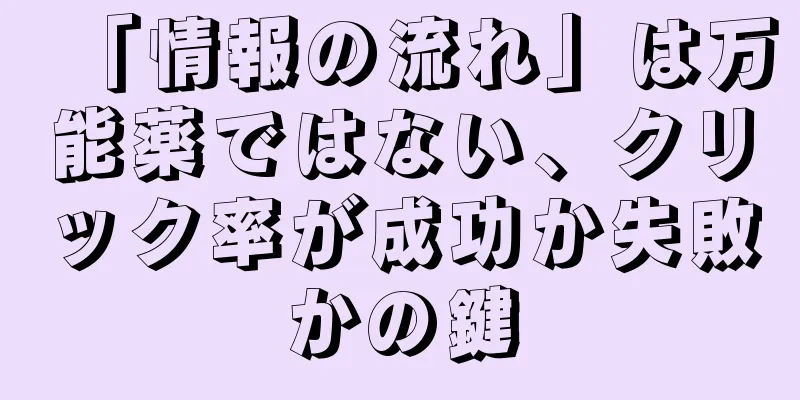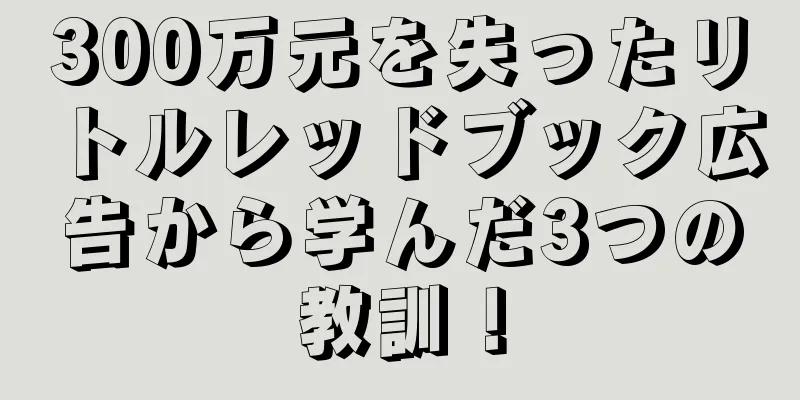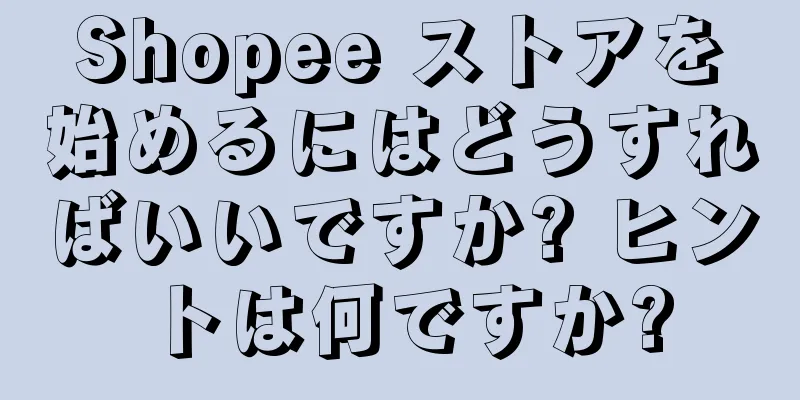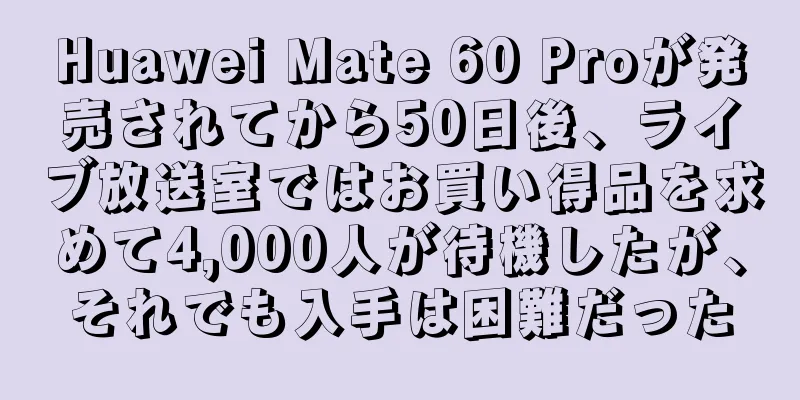共創4.1 - 「消費」の霧を晴らす:第4次消費者時代と共有意識の台頭
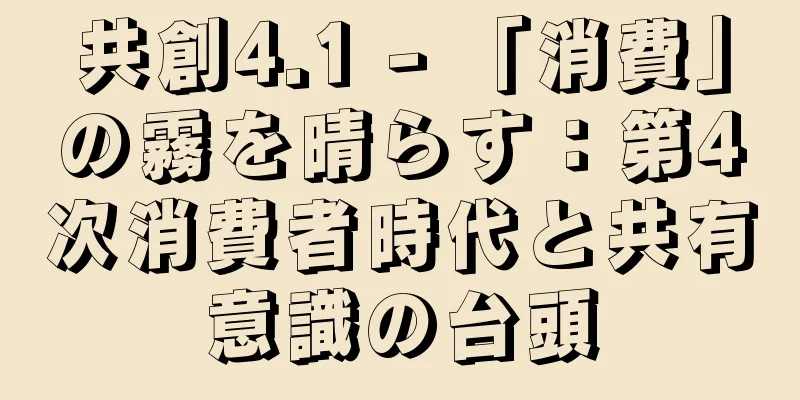
消費、消費者、消費社会、消費市場、消費動向、消費のアップグレード/ダウングレード、消費主義、新しい消費などの概念はどこにでもありますが、「消費」とは本当に何なのか理解していますか? 「共創感覚」を学ぶにはなぜ「消費」を学ぶ必要があるのでしょうか?とても簡単です。 「消費」を理解していなければ、どうやって新たな消費の霧を透かし、安全な未来を見つけることができるのでしょうか? この記事では、ミクロなアプローチを採用し、消費、消費特性、将来の傾向を 6 つのレベルで説明します。
今日はまず、 「消費」とは何か、そして日本の消費の進化と進化について見ていきましょう。次のセクションでは、中国の新たな消費について再認識します。 1. 「消費」とは何か? ——ボードリヤール、ケビン・ケリー、三浦三歩、そして中国のZ世代「consume」という単語が14世紀に英語に登場して以来、その意味は常に進化してきました。 「Con」は「すべて」を意味し、「Sume」は「取る」を意味します。昔、人々の主な消費財は食べ物であったため、「消費する」は「使い切る」、「燃やす」、「食べ尽くす」、「飲み尽くす」を意味し、後に破壊、浪費、消耗などの否定的な意味にも広がりました。 18 世紀以降、「消費」は中立的な形でブルジョア政治経済に入りましたが、その否定的な意味は完全に消えたわけではありませんでした。実際には、それは批判的な姿勢、つまり浪費的で贅沢な社会生活状態を観察し、批判する姿勢を示しています。 ボードリヤールの場合、「消費」はまったく違ったものになります。 1. ボードリヤールの基盤:「消費」は象徴的な属性である1970年、フランスの社会学者ジャン・ボードリヤールは画期的な著作『消費社会』を出版した。 ボードリヤールは著書の中で次のように指摘している。
これを現代語で言い換えると次のようになります。
1970 年の理論、なんと強力でしょう。 2. ケビン・ケリーの「消費」に対する新たな認識 - 「所有」から「参加」へ未来学者のケビン・ケリー氏は、テクノロジーとインターネットの発展が私たちの消費習慣に大きな変化をもたらし、消費が従来の「所有」から「参加」へと移行していると考えています。 人々はもはや商人が提供する商品やサービスの単なる受動的な受取人ではなく、創造者、共同創造者、参加者になっています。彼はこの現象を「シェアリングエコノミー」と呼んでいます。
これらの力は運命ではなく、軌道です。彼らは私たちがどこに向かうのかを予測してくれません。それらは、近い将来、必然的に私たちがどの方向に向かうのかを教えてくれているだけです。 3. 三風秀樹の新しい考え方:「消費」とは達成と無償の喜びである日本の社会学者三浦英俊氏は『第四次消費社会』の中で消費について新たな考えを述べています。 三風秀樹氏は、「消費する」に似た別の単語は「完了する」であると考えています。ここで、「Com」は「すべて」を意味し、「Sum」は「合計」を意味します。動詞として、「Consummale」は完了する、実現する、達成するという意味です。
フランス語でコンソマシオンは「完成」や「達成」という意味もあります。 また、三浦秀樹氏は、社会学の重要な概念であるConsummateの派生語「Consumatory」がポイントだと考えている。これは「自給自足」と訳され、芸術によってもたらされる感動や「虹を見ると心が躍る」といった感情が、手段を講じなくても得られるという意味にまで広がります。 これにより、まったく新しい洞察が得られます。「消費」という言葉は、「使い切る、消費する」という意味だけではありません。 「完璧な成果を達成する」ことも含まれます。より強い推論は、 「消費」が「手段を伴わない一種の自由な喜び」も意味するということである。 最終的に、三浦は自身の考えを明確な理論体系「第四次消費者時代」(詳細は後述)にまとめた。 4. 「インスピレーション」の解釈 - 「消費」は意味のある消費の一種である「インスピレーション」の中で、羅振宇は「消費」と「消費主義」についてある程度詳しく説明しました。 学者の徐志遠氏は、 「今日の社会は、実は物質的な物が不足しているのではなく、意味が不足している。消費の大部分は、実は意味とアイデンティティの消費である」と語った。 実は、多くの人が本を買っても読まないのは、このためなのです。たとえば、ある本に注目し、そのタイトルがとても気に入ったのでそれを購入したとします。一度手に入れると、タイトルの所有感が満たされ、本への関心は終わります。 そのため、羅振宇氏らは、所有すること自体が意味の実現であり、それが新しい消費時代の最大の秘密かもしれないと信じている。 この関連性を続けると、消費主義とは何でしょうか?それは怠惰で贅沢なことではなく、消費を利用して意味の欠如の問題を解決することです。 たとえば、私が Apple の携帯電話やバッグを購入すれば、それが私がどんな人間であるかを証明することになります。これをショッピングとみなすことができるでしょうか?これは意味を買うことです。逆に言えば、それは私が自分で意味を創造する能力を持っていないことも証明しており、既成のものを買う必要があるのです。これを消費主義といいます。 同じことでも、それを消費と見る人もいれば、投資と見る人もいます。 5. Z世代とアルファ世代は追求するものが違う:「消費」は一種の生活主権デジタル化、テクノロジー、アイデアの衝突と融合により、ジグムント・バウマンの「流動的な社会」と個人化の時代が到来しました。 流動的な社会は、自由な流れ、相互のつながり、そしていつでもリラックスできる基盤を提供します。個人化とは、個人が伝統的な集団的社会関係や構造から脱却し、完全な個人的権利を持ち、独立した決定を下し、自分自身の人生を形作ることができることを意味します。 つまり、最終的に、自分がどんな人間になりたいのか、どんな人生を送りたいのかを自分で決めることができるのです。 そのため、これらの新しい人類は、「消費」に対する追求が異なり、受動的な消費者から能動的な人々へ、消費者主権から生活主権へと進化しています(以下は「超感覚リコード」より引用)。
これは、今日、さまざまな小さなユートピア共同体、自給自足、ワイルドな教師、故郷に戻ってビジネスを始める、砂漠に木を植える、国中に横たわる、シティウォーク、ドーパミンの幸福感などの小さな興味の爆発と「百鬼夜行」が見られる根本的な理由でもあります。 さらに重要なのは、これらの新しい人間は、「消費」の意味を「所有して獲得すること」だけでなく、感情的な満足、人生の証言、自己構築などとしても捉えていることです。彼らは「消費」を手段や力として積極的に活用し、さまざまな社会問題に介入し、実践的な行動を通じて社会に良い変化をもたらします。 さて、「消費」とは何なのかご存知ですか?おそらくさらに混乱するでしょう。それは正しいです。なぜなら、「消費」の本質と意味について考え始めるからです。 しかし、「消費」が「物の象徴化」、「達成と喜び」、「参加と共有」、「意味とアイデンティティ」、「生活の主権」のいずれを指すとしても、 「消費」はもはや単に買って使うことだけを指すものではなくなっています。それはこれまでにない魅力と無限の想像力を持ち、より良い未来を意味します。 2. 三浦の4つの消費者時代と消費者価値観の変化ブランドエイプは、数多くの社会消費研究の中で、中国の消費の変化、傾向、将来の可能性をより深く理解したいのであれば、 10年前に三浦秀雄氏が出版した「第4次消費時代」を読むだけで十分だと考えています。一方では、中国の50年間の消費の変化を現象世界で読み解くことができ、他方では、合理的な観点から消費変化の根底にある論理を継続的に探求することができます。 三府秀樹は、産業革命以降の日本の消費を、時間、特徴、態度に基づいて4つの時代に分類しています。 1. 最初の消費者社会(1912-1930)消費背景:経済の繁栄と国の成長。 宝塚歌劇団は1913年に創立されました。日本初の駅デパートは1920年にオープンしました。資生堂チェーンは1923年にオープンしました。サントリーウイスキー/タイガー魔法瓶が棚に並びました。 主なグループ:富裕層と少数の中流階級による消費。 消費志向:高級、西向き。 消費価値観:ステータスを重視した個人消費。 中国をベンチマークすると、改革開放から10年後、1960年代生まれの人々が4大商品を消費し、最初に裕福になったグループになった。 2. 第二次消費社会(1950-1974)消費の背景:経済復興、急速な成長、国民意識の再構築。 1964年東京オリンピック; 1966年トヨタカローラ量産「マイカー元年」 1968年、中国はアメリカに次ぐ経済大国となった。 1970年大阪万博。 主な人口:中流階級の1億人。小さな家族や小さな主婦がたくさん現れました。 消費志向:大量消費(大きいほど良い、大型商品、大都市志向)と家族消費(個人住宅と自家用車に象徴される社会の追求)。 消費価値: 家族と社会のための個人消費を重視する。 中国をベンチマークすると、都市化の加速、1970 年代生まれの人々の消費、1998 年から 2008 年にかけての住宅ブーム、中流階級の出現などが挙げられます。 3. 第三次消費社会(1975-2004)消費背景:経済バブル。人口爆発、格差拡大、金融改革。 1974年のセブンイレブンコンビニエンスストア。 1979年に発売されたソニー初のカセットプレーヤー。 主な層:好景気時代に生まれた独身者(フリーランサー)、個食人気(ひとり飯・インスタントラーメン・インスタントコーヒー)、晩婚化が進んでいる。 消費志向:欧米ブランド、高級ラグジュアリーファッション。
消費価値:個人の私的消費を重視。 中国のベンチマーク: 2008 年に新しい電子商取引小売業が始まりました。個人主義的で自己満足的な国家的傾向。主な消費者は新中流階級と1990年以降に生まれた人々です。 4. 第四次消費者時代(2005年~2034年)消費背景:長期的な景気低迷。人口は減少し、消費は縮小し、住宅問題が顕著になってきています。 無印良品、ユニクロ、蔦屋書店が誕生しました。 主なグループ: あらゆる年齢の独身者。 消費志向:シンプルさ、余暇、ライフスタイルの傾向。日本と地域の傾向;意識の共有の誕生。
消費価値:消費を自己充実のプロセスに変え、人生の意味を持って消費を追求する。 中国をベンチマーク: 2020年から始まる冬季オリンピックの中国ロマンス。新たな貧困と洗練された貧困。退縮して平らになる;課題と不安、憧れと行動、そしてグリーン、環境保護、持続可能性の追求。コアグループ: 1995 年以降に生まれた世代、Z 世代、デジタルネイティブ。
よく見ると、三浦氏の 4 つの消費者時代が、過去 50 年間、特に過去 2 年間の中国の発展と完全に一致していることに驚き、うれしく思うでしょう (次の章を参照)。 3. 第4次消費時代の核心となる原動力は「意識の共有」三風秀樹は、第四次消費時代を牽引する核となるのは「意識の共有」であると考えています。 この見解は、実際にはボードリヤールの『消費社会』とアルフレッドの『人生の意味』を継承しており、後にジグムント・バウマンの『流動社会』とケビン・ケリーの『シェアリング・エコノミー』と統合されています。 三浦翔氏の「意識の共有」を理解するために、3つの進歩的なロジックが役立ちます。 1. 「共有意識」とは何ですか?
まとめると、「共有」を重視する社会では、人と人、人と社会の関係がより重視され、そこから「社会意識」が生まれます。 2. 個人意識から社会意識へ
もっと簡単に理解すると、「幸せ」から「嬉しい」への変化です。 例えば、「昨日友達とテーマパークに行ったんだけど、すごく楽しかった」と「昨日友達とテーマパークに行って本当に幸せだった」を比較すると、後者は友達に焦点が当てられていることがわかります。出会えたという実感や、お互いの関係性のレベルは、幸福だけでは体験できません。 例えば、現在の経済的な消費行動では、人々は基本的に、意味があると思うものにお金を使います。そのため、これまでとは違う何かに出会って「これで幸せになれる」と感じたときだけ、お金を使う意欲が湧いてくるのです。 これからの時代は、人と人、人と社会のつながりがますます大切になってきます! インターネットからの画像: 北辰青年WeChat 3. 利己主義から利他主義へ
さらに言えば、「共有意識」のもとでの利他主義も一種の「分散」意識です。こうしたローカル意識やサークル意識は、必然的に反中央集権主義や反権威主義の意識を生み出しますが、これはまさにケビン・ケリーの視点、つまり未来へのロードマップである「群集思考」と一致しています。 つまり、消費は純粋な物質的消費から、感情的な体験や精神的価値に重点を置いた消費へとようやく移行したのです。私たちは、個人の幸福から、非私的な価値観、精神的な幸福、そして社会的幸福へと移行してきました。 4. 第四次消費者時代の次に何が来るでしょうか?三風秀樹氏は、「共有」「利他主義」「社会」という3つの特徴がさらに深化していくと考えており、企業や政府はさらなる責任を負うべきだと考えている。
最後に三浦三保氏は、今後は「シェアリング、社会的責任、社会実験」の消費が世界の消費の主流になるだろうと結論付けた。人々は互いに必要なリソースを提供し合い、個人の利益を最大化し、社会的責任を最大化します。 4. 日本の第四次消費時代と「シェア意識」が生まれた理由以上の結果が単なる論理理論のレベルに落ち込むことを防ぐためには、日本の共通意識がなぜ生まれたのかを分析する必要がある。 「経済環境の悪化」 「出生率の低下」 「高齢化の加速」による若者の自己実現のチャネルの閉ざしに加え、日本の第四次消費時代の到来には、 「デジタル社会」と「消費の反省」という二つの重要な要素がある。 1. 情報化とデジタル化は、意識の共有の継続的な拡大の基盤である
結果はどうなりましたか?知識と情報の獲得にもっと注意を払います。知識と文化的意味合いをより重視する。社会的な意識をより強く伝え、構築していきます... 2. 国家の反省と消費の指針三浦秀夫、山崎正和、柳宗悦、原博之、山本理顕、上野千鶴子、稲盛和夫、増田宗昭、田中伸彦、山口周…、学者、芸術家、音楽家を問わず、あるいは起業家、デザイン界の巨匠、ブランド関係者らが、当時の日本の消費状況を振り返り始めた。彼らは専門知識と姿勢で消費を解体し、導き、変えました。
最も有名なのは原研哉さんと宮崎駿さんの二人です。 原研哉の実践:「目を大きく開いてイノベーションを模索する熱から心が冷め、体温が平熱に戻ると、周りの物事をじっくりと見る余裕が生まれます。」
宮崎駿は『千と千尋の神隠し』の中で、千尋が迷い込んだ異界こそが現実の日本社会であると明確に指摘しており、私が描写した銭湯は実は日本そのものなのです。
上記のガイダンスにより、さまざまな階層の消費者も反省し、さらに実践的になっています。
日本の消費に対する反省は、物質的・時間的軸を重視する欧米の時代から、東洋的な精神的・空間的軸の探求と拡大へと移りつつあります。 理由を理解すると、「意識を共有する」結果は明らかです。第4の消費者時代のイデオロギーの核心を構成し、それを説明する適切な言葉はもうありません。 余談ですが、ミュラ・ヒドオと他の人たちが日本の消費を反映していたとき、中国の公の知識人と専門家は何をしていましたか。金持ちはワインと肉を楽しんでいますか?衝撃的なことを言うまで止まらない?熱意を後押ししたり、悲観論を表現したりしますか?消費を奨励しますか?盗作?悪態をつく?ゴシップ?ライブストリーミング? …….. Luo Xiangは、「13の招待状」で非常によく言った: 「多くのrog慢な見解は、普通の人々の基本的な常識と矛盾しています。技術的な議論には何の問題もありませんが、人々の良心と対立しています。」 著者: Brand Yuan、WeChat 公開アカウント: Brand Yuan (ID: brand-yuan) |
>>: ココナッツの木からサンザシの木まで、「男性向けセックスマーケティング」がなぜこれほど人気になったのでしょうか?
推薦する
ライフン、ヴィシー、ボシデンは、戦略的な新製品でどのようにしてダブル11リストに載ったのでしょうか?
今年のダブルイレブンで主流プラットフォームがどこに焦点を当てるかご存知ですか?さまざまな分野のブラン...
Amazon はどうやって人気のない商品を選ぶのでしょうか?何かヒントはありますか?
現在、Amazonに出店する業者が増えています。そのため、販売するのに適した商品を見つけるのは非常に...
ブランドNo.1: 求人コンペシリーズ009
商業競争の激しい戦場において、ブランドは正確なポジショニングと価格戦略を通じてどのように市場に勝つこ...
Amazonの売上総利益と純利益の違いは何ですか?
誰もがビジネスを行う際に独自の利益を計算するので、Amazon でストアを開く人は誰でも、Amazo...
Shopify はどのモデルに属していますか? Shopify モデルの紹介
現在、Shopifyはますます増えており、独立系ステーションの利点を明確に理解しているセラーの友人も...
製品マーケティングの終焉はコリアンダー?
コリアンダーは好きですか?答えが何であれ、コリアンダージュースのグラス、コリアンダーピザ、あるいはコ...
これら 3 つのブランドは私にこう言いました。「自分を他の人と比較しないでください。これは単なるコラボレーションです」 |抗不安スペシャル
ソーシャルメディアの時代では、私たちは自分を他人と比較する傾向があります。この不安解消スペシャルでは...
Etsy ストアを移行するプロセスは何ですか?予防
Etsy プラットフォームで何かを販売したい場合は、その商品が自分で作ったものか、またはツールを使用...
カスタマーサクセス部門が再びカスタマーサービスになった場合はどうすればいいでしょうか?
なぜカスタマーサクセス部門が再びカスタマーサービスになったのでしょうか?カスタマーサクセス部門は、カ...
貿易工場が直面する問題と解決策
貿易工場が直面する問題と解決策 業界は激しい競争にさらされており、対外貿易の注文価格は何度も下落して...
Amazon メンバーシップの自動更新をキャンセルするにはどうすればいいですか?手順
現在、多くの友人がAmazonプラットフォームを利用して、自分で海外製品を購入し始めています。同時に...
Amazonの商品ランキングが表示されない場合はどうすればいいですか?なぜ消えてしまったのでしょうか?
Amazonで商品を販売する場合、常に商品のランキングに注意する必要があります。商品のランキングが高...
なぜラッキンコーヒーはプライベートドメインで毎年巨額の利益を上げているのに、あなたはプライベートドメインに多大な労力と資金を費やしているのに、まだ利益を上げられないのですか?
なぜラッキンコーヒーのプライベートドメイン事業は高い成長を続け、業界の学習のベンチマークにまでなれる...
Taobao 88VIPがメジャーアップグレード、JD.com PLUS会員と真っ向から競合するのか?
有料会員として、今年は誰が優れているでしょうか?毎年のダブル11は、アリババとJD.comにとって下...
越境電子商取引でシンガポールで販売するのに適したものは何ですか?商品の選び方は?
越境ECプラットフォームで店舗を開くときに最初にすべきことは、良い場所を選ぶことです。シンガポールは...