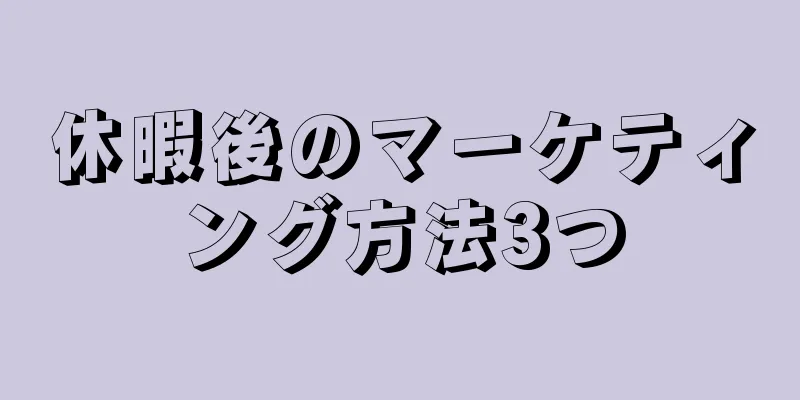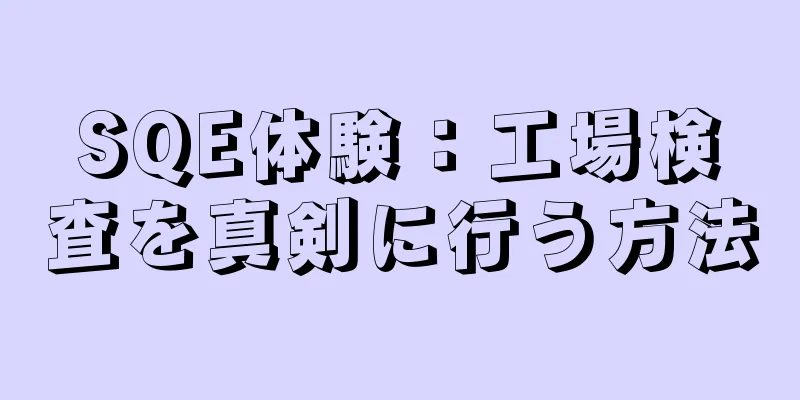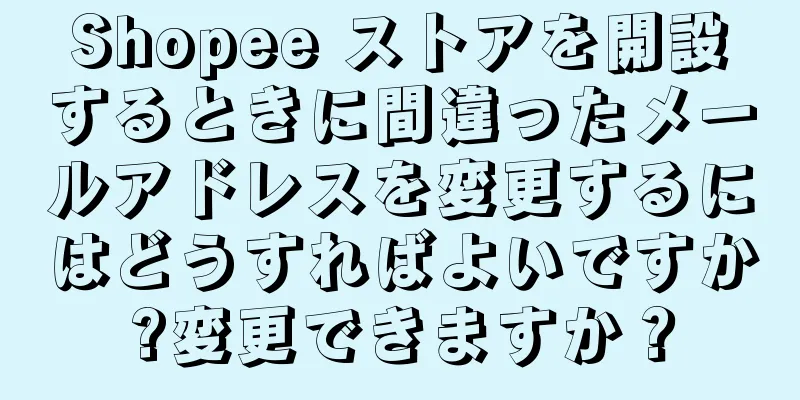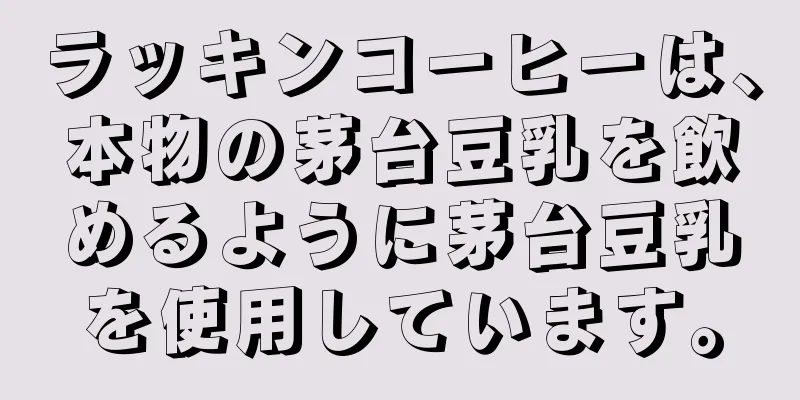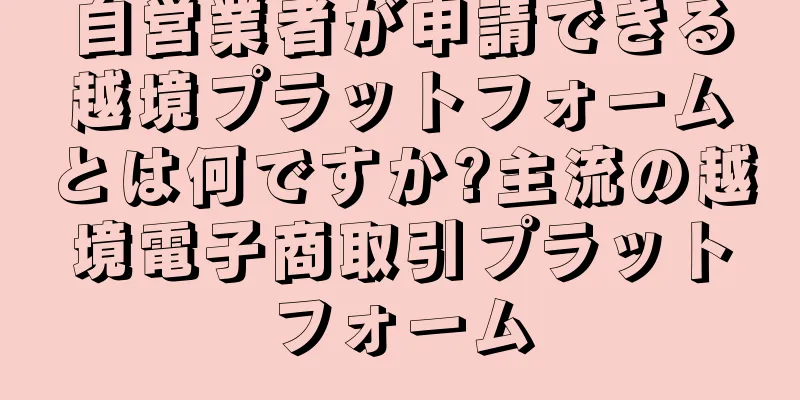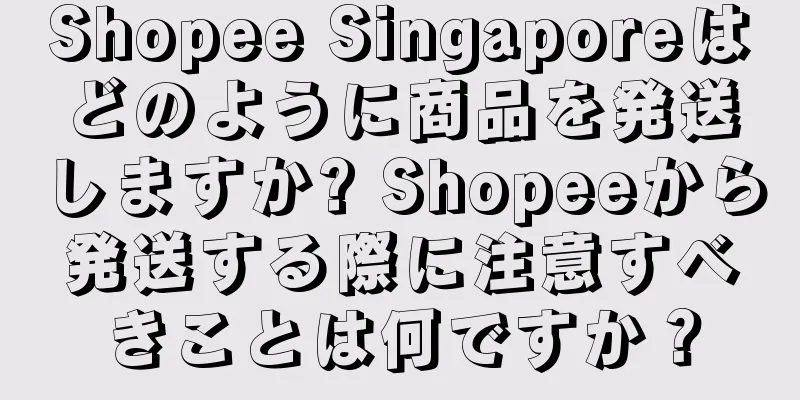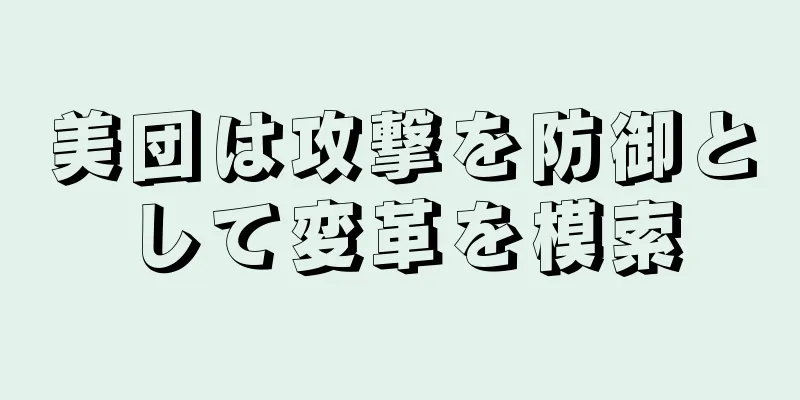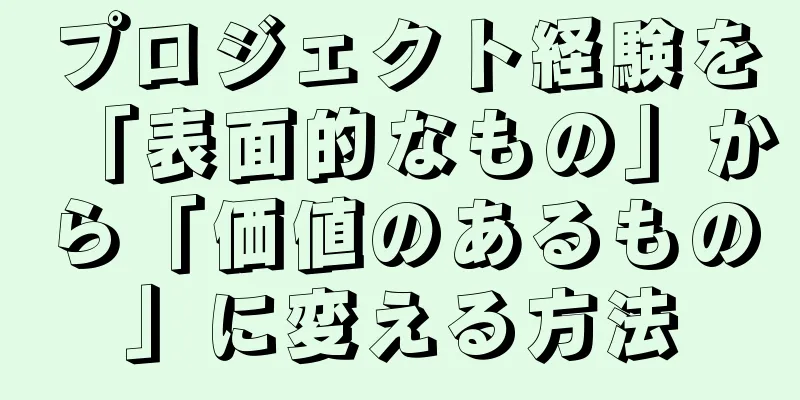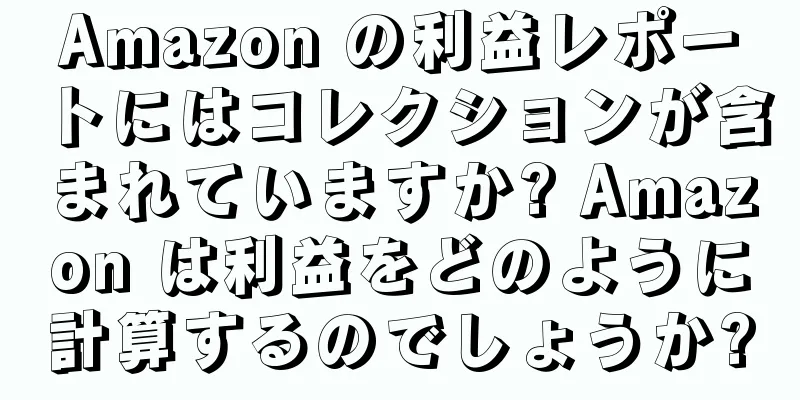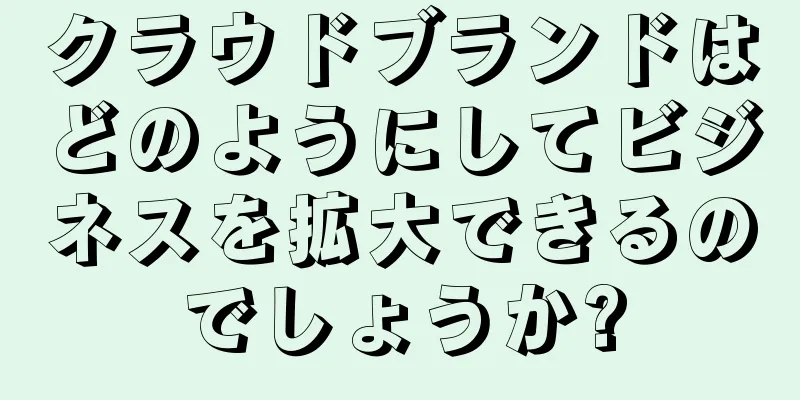新たな消費が日本へ、若い女性をターゲットに
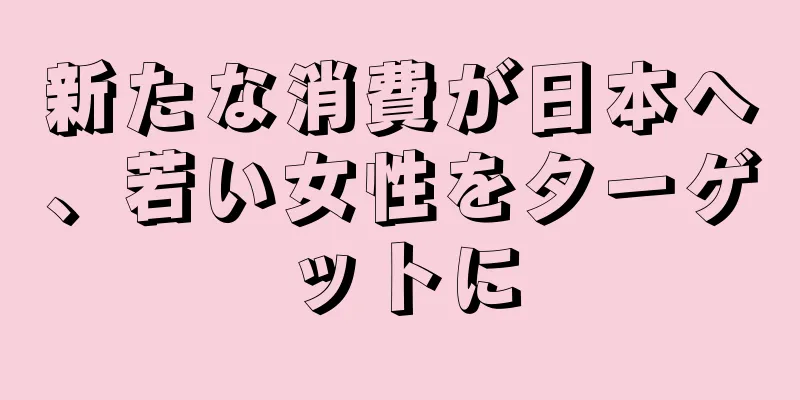
赤と白のポスターが目を引く「ミクシュアイスシティ」が日本市場を席巻した。 「スノーキング」の横の列は若い女性で混雑しています。濃い青色の華西子の広告が原宿バスのあちこちに貼られ、ハイヒールとロングスカートをはいた買い物客の横を通り過ぎていく。 ByteDance が所有する明るい黄色のライフスタイル プラットフォーム lemon8 が日本で台頭しており、その主力も人生における絶妙な小さなサプライズを追い求める若い女性たちです... 中国消費財が海外から日本に進出する兆しが見えているが、それは現地の若い女性のライフスタイルと深く関係しているようだ。 日本の作家、荒川和久氏は著書『超ソロ社会 独身の国日本の衝撃』の中で、2035年までに日本の人口の半数以上が「独身」を実践するだろうと予測した。 「一人でも豊かに美しく生きる」というコンセプトを掲げ、経済的に自立した未婚・未婚の日本人独身女性が多く、潜在的な消費を牽引している。 「寝心地が良い」「実用的」「必要な時以外は買わない」といった日本の一般的な市場の消費ニーズの背後に、現地の若い女性のニーズが本当に掘り起こされているのだろうか。独身の日本人女性は中国の消費財業界にどのようなチャンスをもたらすのでしょうか?野心的な中国の新しい消費者ブランドは、海外に進出することで利益を上げることができるでしょうか? 消費が海外から日本へ向かうという新たなトレンドの中で、中国ブランドはどのようなチャンスに直面しているのでしょうか?地元の消費者やパートナーは中国のブランドに対してどのような態度を取っているのでしょうか? 1. 「新しい消費トレンド」における日本の女性中国の化粧品ブランド「華喜子」は最近、日本の原宿で「フラッシュモブ」を開催した。 日本の若者の集いの場である原宿の@cosme旗艦店の1階エントランスは、30平方メートルに満たない小さなスペースで、写真撮影やチェックイン、化粧品の試用や購入のためにやってくる日本の若者や地元のネットセレブ、日本の雑誌編集者で賑わっている。 モモさんは、日本の本州最西端にある山口県に住むセルフメディアブロガーです。彼女は原宿で行われた花子のメイクアップ発表会に出席するためだけに、自費で山口県から東京まで旅し、近くのホテルを早めに予約した。中国色が強いブースで、彼女はまるで憧れのアイドルに会って念願を叶えた小さなファンのようだった。 日本の消費市場には長い間「ミニマリズム」や「無欲」の雰囲気が浸透していますが、モモさんのように美との出会いを楽しみにしている若い女の子のファッションブロガーは今でもたくさんいます。中国風の海外ブランドの新たな消費傾向は、人々の生活にさらなる斬新さ、洗練さ、美しさをもたらしました。 日本の原宿にある華西子の巨大看板@cosme 化粧品ブランドだけでなく、最近では日本に輸出される中国製品も多数、若い女性の消費市場に狙いを定めている。 ヘアアイロンを生産するある会社の海外展開担当者は下光通信に対し、今年初めから自社で生産する洗顔料を日本に販売する準備を進めており、周辺の多くの工場も国産のヘアアイロン、美容機器などの小型美容・化粧品電子製品、さらには化粧品用コンタクトレンズを日本、韓国、東南アジア市場に販売する計画で、その多くは電子商取引の形態をとっていると語った。 一般的な美容・化粧品カテゴリーに加え、ByteDanceのlemon8も日本では大きな影響力を持っています。日本のバイトダンス株式会社が主導するこのソーシャルメディアソフトウェアは、ShareeからLemon8に名前を変え、現在「リトルレッドブックモデル」として日本の女の子たちの間で熱狂的に模倣されています。 「lemon8は若い女性の誘致に力を入れており、チェックイン文化を利用して消費に影響を与えることにも力を入れています。ここの若者は学習が早いです。購入する前に、最近オープンした新しいデザートショップがあるかどうかなどをチェックするのは当然です。コンテンツの多くは、女の子の心を本当に打つことができるカテゴリキーワードです。」日本を拠点とするブロガーのリン・ピンさんはXiaguangsheにこう語った。 リン・ピンさんは日本に12年間住んでおり、Weiboで560万人以上のフォロワーがいる。彼女は、小紅書のような「ちょっとしたサプライズ」や「ちょっとした幸せ」が、日本の若い女性の間で大きな市場を持っていると信じている。 「本当にコンテンツの宝庫です。実際、Lemon8 のトラフィック アルゴリズムとグループ化は、Xiaohongshu よりも具体的だと感じています。たとえば、コーヒーが好きなら、さまざまなコーヒー コンテンツがプッシュされます。」 日本の女の子に人気のお店訪問ノート 画像出典: Lemon8_Japan 「これはまだ消費主義の時代です。日本の若者、特に女性は視覚社会に生きており、オンラインの宣伝の影響を受ける主なグループです」とリン・ピン氏は語った。 ショートビデオが世界的なソーシャルメディア現象となるにつれ、日本の若者の間でショートビデオに対する認知度が高まり、このマーケティング手法が徐々に受け入れられ始めています。もともと日本人は紙媒体や新聞が好きでしたが、ここ2年ほどでオンラインソーシャルメディアでのコンテンツマーケティングがますます人々の生活に影響を与え始めています。 日本の女の子は、購入する前にYouTubeやInstagramのレビューやブランドサークルを参考にします。 林萍は東京・原宿で行われた花錦のフラッシュモブイベントに参加した後、これが中国ブランドの日本での「大規模な海外デビュー」の一つであり、多くの現地の日本人女性の注目を集めていると信じています。 実際、リン・ピンは原宿の@cosmeモールで行われる日本の美容ブランドのイベントに頻繁に参加していた。彼女はまた、「現在、このような場所でブランドプロモーションを行っているブランドのほとんどは日本のブランドであり、そのほとんどは大手ブランドです」と認めた。 日本の東京にある原宿表参道は、交通の便がよく、ショッピングモールが数多くあることから、多くの顧客を魅了しています。中国ブランドが地位を獲得し、注目を集めるのは容易なことではありません。 その中で、表参道は日本の「新興富裕層」が集中しているのに対し、原宿は若者が多く集まっています。全体的に、15歳から40歳までの日本の女性にとって、このエリアは常にお気に入りのファッションの聖地であり、特に中国の海外ブランドのオフライン決済に適しています。 2. 日本には中国製品に対する消費者の購買力があるか?「中国ブランドは日本では依然として魅力的だ。国ごとの制度や文化の違いを反映できるブランドもある」海外進出する日本企業のコンサルタントとして働くラオ・タオさんは、下光社にこう語った。 「しかし、1990年代生まれの日本人はコスト効率を重視する傾向があり、それがブランドプレミアムを圧迫し、ブランドやその国や地域に対する感度を低下させている。」 日本で長く暮らしている陳佳さんも同様の印象を抱いている。 彼女の意見では、多くの日本の友人は、lemon8 が実は中国の会社が作ったアプリだということすら知らないそうです。 彼女は大学卒業後に日本に留学し、ここ数年、海底撈、那雪、米蔭冰成、華志霄、華曦子などの中国の消費財ブランドが日本市場に「上陸」するのを目撃してきた。 陳佳さんは「私のクラスメイトは買い物をするときに流行を盲目的に追うことはありません。品質には特に気を配りますが、ブランドの原産国についてはあまり気にしません」と語った。言い換えれば、日本の若い世代の消費者は非常に順応性が高いということです。ブランドが中国発祥だからといって、「買う」とか「買わない」という判断はしません。 最終的に購入の決定に影響を与えるのは、「製品が自分に適しているかどうか」と「自分の好みに合っているかどうか」であり、これらは製品自体の品質レベルに関連する要素です。 「中国ブランド」に惹かれる人の多くは、中国海外ブランドだからこそ、写真を撮ってみたい、撮ってみたいという中国人や日本に留学している留学生たちです。 時系列で見ると、日本市場に最初に参入した中国製品は、ハイアール、ハイセンス、レノボなど大手商用・民生ブランドでした。 「日本の会社に入ると、そこで使われているマルチメディアシステムがレノボ製であることに驚くでしょうし、ホテルに泊まれば冷蔵庫がハイアール製であることに気づくでしょう」と陳佳氏は語った。今後はAmazon Japanでも中国製の3C製品や携帯電話周辺機器を多数ご覧いただけるようになります。 近年、海底撈に代表される中国の外食産業も日本市場に深く進出している。 「最初は、海底澳に行くのは中国人だけだった。今では、そこに行けば、客の20%以上が日本人だと分かる」と陳佳さんは下光通信に語った。火鍋だけでなく、東京や大阪など日本の主要都市にある中華系スーパーも日本人にとても人気があります。 「日本人が中国の調味料を買っている姿をよく見かけます。」 1990年代以降、日本は「低欲求社会」に入り、全体的な消費意欲は低下しており、無印良品に代表されるミニマリストブランドが登場した。日本の社会学者三浦英俊氏は『第四次消費時代』の中で、2015年から2034年までを日本の「第四次消費段階」と総括し、この段階における日本の消費特性は「共有、利他、簡素」であると主張した。 日本の評論家大前研一氏は著書『低欲求社会』の中で、日本の消費者の消費欲求が低いのは高齢化と出生率の低下が原因だとしている。 しかし、これは日本の若者の消費市場が疲弊していることを意味するのでしょうか?実際、日本の視聴者ユーザーの年齢と性別の分布には大きな違いがあります。 日本の年齢構成によると、35歳以上の消費者は購買力が強く、高品質のブランドを求める傾向があります。中国の海外ブランドがこの層の人々を引き付けたいのであれば、長期的かつ継続的な投資が必要になるかもしれない。 日本の若い女性は、トーンやファッションをより追求し、よりオープンで包括的であり、「爆発的な商品」やソーシャルメディアのプロモーションに対してより友好的です。しかし、無視できないのは、その消費能力には限界があり、自然と上限があるということです。 「消費意欲は社会全体で低下しており、最後に低下が見られるのは女性、特に若い独身女性だ。」ラオタオは依然として日本市場に対して比較的自信を持っている。 彼は、本質的には経済基盤が上部構造を決定し、日本の若者は依然として強い消費力と基本的な消費財を試してみたいという欲求を持っていると考えています。 ミクシューアイスシティの日本進出も決して例外ではありません。日本の新宿では、ココとハッピーレモンが地元の人々に長く親しまれているお茶のブランドであり、ゴンチャは日本で繁栄しています。 食品消費に関しては、本質的に反循環的であり、デザート、紅茶、コーヒーなどの消費財の小売における社会の女性グループの消費習慣は、ある程度、不可逆的です。経済が回復すれば、消費意欲はさらに強くなるばかりだろう。 多くの中国のトップビューティーブランドの海外展開を支援しているMoldBreakingが、Huaxiziフラッシュモブの企画と実行を担当しています。彼女たちは下光社にこう語った。「海外に輸出される中国製化粧品は、16歳から28歳の日本の若者に比較的よく合っています。彼女たちは実際、外国製品に対して非常に受容的です。彼女たちは初期には韓国のブランドを購入していましたが、今では中国やタイのブランドも購入しています。実際には、反抗的な感覚はありません。」 3. 中国の消費財はグローバル化しており、参入する好機となっている「この1年、特に今年に入ってから、日本に進出しようとする中国製品が増えていると感じています。明らかに増加しています。」海外の販売業者であるロマンさんはXiaguangsheにこう語った。以前は、日本市場は東南アジア市場に比べて成熟しており、自社製品の競争力が十分でなければ日本市場への参入は難しいと考えていました。 しかし、今年は一般的に日本に行くのに「絶好の時期」だと考えられています。 一方で、日本円の世界的な通貨優位性を考慮すると、日本の賃貸コストや人件費の割合は弱まってきています。だからこそ、日本の製造業各社が全会一致で従業員の賃上げに合意し、「賃上げの波」が到来したのは今春になってからだった。しかし、全体としては、日本でのビジネス展開は「労働力の高い市場」という印象から「費用対効果の高い場所」という印象に変わってきています。 「5年前と比べると、中国ブランドは安堵のため息をつくことができる。日本の従業員の給与に関して言えば、過去5年間で大きな増加はなかった。」リン・ピンも同様の観察結論に達した。 日経中国版ウェブサイトによると、日本総合研究所の山田久也氏は「日本の賃金は低い水準にある」とし、国内の「賃金と物価の上昇の好循環」はまだ実現されていないとみている。 さらに、地元の人々が国産品を「粗悪品」と心理的に決めつけていることも、徐々に解消されつつある。多くの日本の消費者は、中国ブランド製品の多くが品質が良く、保証されており、デザインやファッション性にも欠けていないと認識し、中国ブランドに対する印象を変えています。 日本の顧客と頻繁に取引する張楽氏は、多くの現地ブランドと提携している。「彼らは、日本市場にとって新しいパートナーやブランドに対してあまり反応しません。そのため、初期の確認作業は非常に面倒で、スタッフのエネルギーをかなり消費します。しかし、この段階を一度乗り越えれば、その後の運営や利益は実にスムーズです。」 現地のブランド、チャネル、オフラインと競争するプロセスは、日本に輸出される中国の消費財の一種の磨き上げと改良でもある。例えば、日本の大型ショッピングモールやドラッグストアへの出店が許可されるブランドの場合、市場から商品の詳細に関する要求が多く、さらには商品パッケージの開封、パッケージの透明性などにも出店要件があり、かつてはブランドオーナーに多大な頭痛の種となっていました。 しかし、厳しい基準と成熟した競争の下では、これは製品の進化がより繊細になるブランドアップグレードのプロセスであることを認めなければなりません。 「海外に進出する中国ブランドがあらゆる年齢層に影響力を広げたいのであれば、ブランドを磨き続ける必要がある。」長年にわたり中国化粧品の日本への輸出に携わってきた郭希若氏は、「ブランド輸出」こそが、今後の中国消費財の日本市場への輸出の希望であると語った。これと反対なのが、低価格、ホワイトラベル、低品質の商品であり、彼はこれを「典型的な投機的行動」と呼んだ。 この種のボーナス期間戦略は、東南アジア市場ではまだチャンスがある可能性があり、多くのプロモーション労力を節約できる可能性もあります。 「日本はすでに非常に飽和した市場だ」と郭希若氏は語った。 「しかし、停滞しているわけでもありません。本当に優れた新しいブランドが生まれる余地はありますが、ただラベルを貼って『日本でふざけていけば大丈夫』と考えることはできません。」 海外に進出する多くの人々の見解では、「日本のビジネス環境は全体的に良好である」。日本ではブランドプレミアムが低下し続けていますが、ブランドの特徴は依然として消費者に新鮮さをもたらすことができます。 日本の女性をターゲットにした海外消費カテゴリーにおいて、現在明らかになっている可能性は、高品質、国を強調する必要のないブランド、単一経済との関連性の3つの側面に集中しつつあります。 Mixue Bingcheng から Huaxizi まで、オフラインで本当に足場を築き、日本の消費者の心に印象を残すことができる中国の消費財は、ブランドを基盤として海外に進出するものであることは事実が証明しています。 日本に定住した船員は、日本の市場を大きなスポンジケーキに例えた。「大きな一片は食べられませんが、スポンジのように真ん中に隙間がたくさんあり、中に入るのに時間がかかります。」 著者: 郭昭川 出典:WeChatパブリックアカウント「Xiaguangshe(ID:Globalinsights)」 |
>>: 徹底分析:3つの世界的なトレンドが長期的ブランディングの時代の到来を告げる
推薦する
あなたがクッキーショップのオーナーだったら、インターネットの考え方をどのように活用してクッキーを販売しますか?
現在の雇用情勢は楽観的ではなく、少ないコストで利益を生み出すことを目的としたライトウェイト起業を中心...
小紅書の11の戦略を包括的にレビューします。新規加盟店はどのように選択すればよいでしょうか?
小紅書の使い方は実に多様であることがわかりました。この記事は、初心者の商人に適した 11 の方法を見...
2023年はついに本当の「ビデオアカウントの年」となるのか?
WeChatビデオアカウントの人気はここ数日高いままです。 Cポジションビデオアカウントは2023...
30人以上の最前線のトレーダーと会った後、プライベートドメインに関する20の新しい見解をまとめました
「プライベートドメイン」はトラフィック時代の最もホットなトピックの1つです。本稿では、プライベートド...
1年経ってもAmazonで商品を返品できますか? Amazonで商品を返品するには何日かかりますか?
消費者と販売者は、返品ポリシー、特に「Amazon で 1 年後に商品を返品できますか?」という質問...
2024 年に予測される 100 個のキーワード |技術革新(11-20):新しいアイデンティティ、共感技術、匂いのデジタル化、人間と機械の共生
2024年の開発のキーワードは何でしょうか?著者の技術革新に関する予測を見てみましょう。 2024年...
Amazonブルーバッジを取得するにはどうすればいいですか?メリットは何ですか?
Amazonで買い物をするバイヤーは、一般的に小さな青いラベルが付いた商品を優先します。このような商...
中国のミルクティーがヨーロッパを征服した歴史
茶葉からミルクティーまで、中国の味は世界を征服する新たな旅に乗り出しています。著者は、ヨーロッパ各地...
データ分析を行う際にビジネスに実現可能な提案を行う方法
この記事では、製品の価格を引き上げたいと考えているインターネット電子商取引会社の実際のケーススタディ...
Amazon は新製品のトラフィックをいつまでサポートしますか?どうしたの?
Amazon マーチャントにとって、実は新製品サポート期間があります。Amazon マーチャントはこ...
ティックトックが美団のケーキに食い込む
デジタル化の波に押されて、地元ビジネスの競争環境は変化しています。 MeituanとDouyinの競...
新しい Shopee ストアで商品を誰も見ない場合はどうすればいいですか?どのように処理しますか?
現在、Shopee にストアを開設するマーチャントがますます増えています。Shopee マーチャント...
小紅書は守るのは簡単だが、攻撃するのは難しい
小紅書は評価額が170億米ドルに達する新たな資金調達ラウンドを完了したと報じられており、これは同社の...
まだXiaohongshuにSOPを投稿していない場合は、ぜひご参加ください
活気に満ちたソーシャルプラットフォームであるXiaohongshuでは、インフルエンサーマーケティン...
10人以上のブランドマネージャーへのインタビューで5つの新しい618戦略が明らかに
618がもうすぐ登場します。この期間中、プラットフォームは互いに競争し、ブランドは互いに競争すること...